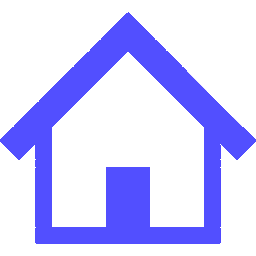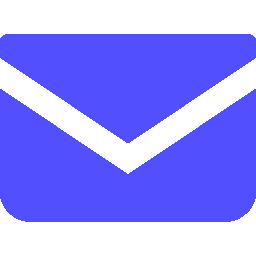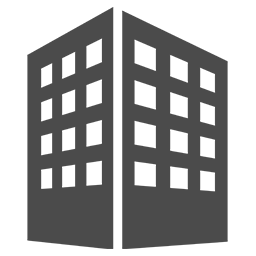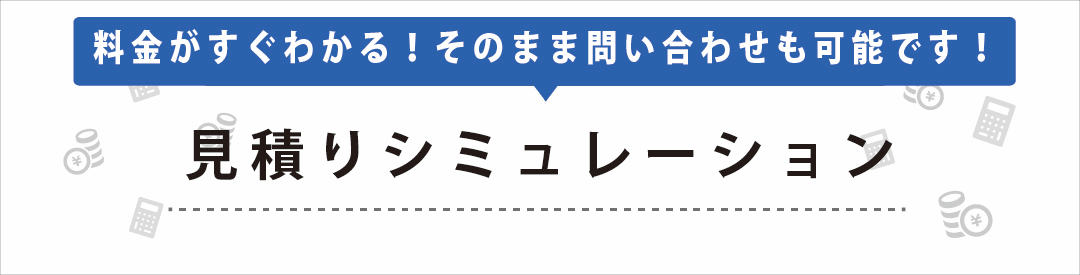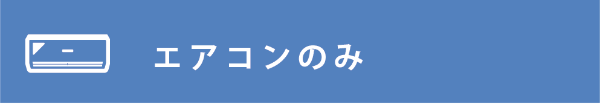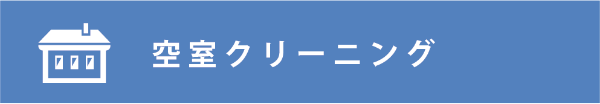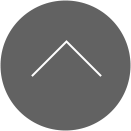コンクリート表面がなぜ表面に白い物が浮かび上がる?
更新日:2024年04月18日
コンクリート表面の白華現象
モルタルやコンクリートあるいはこれらの二次製品の表面、タイルやブロックの目地に生ずる白い綿状の吹出物あるいは斑点を白華という。エフロレッセンス、鼻たれあるいは略してエフロともいう。白華は、セメント中に含まれる硫酸塩、炭酸塩が水に溶けて表面に現れ、水が蒸発して析出した塩で、炭酸カルシウムとして析出されることが多い。不均質な施工による材料分離や透水しやすいコンクリートで発生しやすい。また、冬季に打設したコンクリートに発生しやすい。
どのようにしては現象が発生するのかそのメカニズム
コンクリートなどの内部の水と共に溶けた物質が、濃度のむらなどにより空間へと溶け出した原因物質が表面に移動し、大気中の二酸化炭素と化合して表面に白い粉としてれる現象を現れる白華(エフロレッセンス)と言います。コンクリート製品、レンガには起こりうる現象です。ハウスクリーニングではしばしば窓にこの白華現象(エフロ)が付着して取れない汚れとしてご連絡頂く事があります。特に冬季や、梅雨時期など比較的湿度が高い等の気象条件で発生しやすく、現在この現象を完全に防止する方法は無いと言われていますしかしながら、万一白華が発生しても、製品上の欠陥ではなく、耐久性が低下してしまう事はありません。
コンクリートが硬化する過程で、水とセメントが反応して、含水ケイ酸カルシウムが形成され、同時に多量の水酸化カルシウム ( Ca(OH ) 2 )ができる。コンクリートが乾燥すると、コンクリート中の含まれてた余剰水なに溶解したこの水酸化カルシウムが、余剰水と共にコンクリート表面に移行し、余剰水が蒸発して表面に水酸化カルシウムが残存する。この水酸化カルシウムは、二酸化炭素 ( C O 2 )を吸収し、水に不溶な炭酸カルシウムへと変化させる。建設初期に発生する白華現象は、このメカニズムによるものが多くこれを第一次白華と呼ぶ。また、セメントの硬化は時間の経過に伴って次第に速度は遅り長期に渡って硬化し続ける。その結果、水酸化カルシウムが長期に渡ってコンクリートの内部から放出されることとなる。また、経年劣化などによってコンクリート内にひび割れなどから雨や結露による新たな水が浸透すると水酸化カルシウムを溶解し、上記のメカニズムにより表面に白華現象を生ずる。比較的長い年月をかけて発生する白華現象を、第二次白華という。打設直後のコンクリートのpHは12以上の強アルカリですが、エフロレッセンスの主成分である炭酸カルシウムのpHは8.5~10程度の弱アルカリ性です。
このように第一次白華は、コンクリート中の水酸化カルシウムがコンクリート内部の余剰水に溶解して表面に移動するため、コンクリート表面の全面に渡って生ずることが多い。しかし、第二次白華は、コンクリート中のヒビなどに応じてその隙間から水酸化カルシウムが浸透水が出る事が多いためコンクリートの密度の違いによって水が浸透しやすい部位にだけ局部的に発生する場合が多い。
白華現象の防止対策
エフロは先述の通りコンクリートの内部から出てくる余剰水が二酸化炭素と化学反応を起こして発生する事が多いです。そのためいかにその水を逃がすかが大切なポイントとなります。考えられる対策は以下の3点ですが、いずれも施工段階から検討が必要です。
①約2%程度の横断勾配の確保し排水路への流す
②コンクリート路盤などに水抜き穴の設置
③地下水位が高い場合は地下排水を行う
まず舗装表面で約2%程度勾配を確保して排水や雨水を側溝に排水します。また、舗装各層(路床、路盤、敷砂)についても横断勾配を設けるなど舗装体としての排水処理を適切に計画し、余剰水が必要以上に表面に出ないように工夫します。既に出来上がったコンクリート路盤などは、舗装に浸透した雨水によって敷砂の含水比が高まり、エフロが発生することが多い傾向にあります。この場合には、2 ~ 3 ㎡に1箇所程度の割合で水抜き穴(直径10cm程度)を設けて敷砂に浸透した水を円滑に排水させることが必要です。水抜き穴には鉄道のレールなどと同じ要領で砕石などを詰め敷砂の流出防止を図ります。次に地下水位が高い場合は、地下排水を行って路床、路盤、敷砂の排水を行います。
コンクリート中の水酸化カルシウムが水に溶けて表面に移行し、大気中の炭酸ガスを吸収して白華は生ずるので、水を表面に移行させないこと、および二酸化炭素など炭酸ガスと接触させないことが対策としては有効でが、コンクリート中の水の移動を阻止することや、コンクリート表面に欠陥のない緻密な膜を形成させることは現実の対策としてかなり難しく、完全に白華を防止することは難しい。従って、防止対策に準じた方法で、今現在は完全に防止する事は難しく、白華現象をできる限り限定的に抑える為の抑制対策を講じることが必要となる。 コンクリート中の余剰水の表面への移行を少なくする対策としては、単位水量をできるだけ小さく抑えること、およびコンクリート表面の急激な乾燥を避けること等が上げられる。使用する水量自体が少なくなるよう使用材料および配合を決定し、ブリージングの少ないコンクリートとするのがよい。また、湿度や風の影響により、打った直後のコンクリートは表面が急激に乾燥しないよう、十分に湿潤養生を行うのがよい。この場合、湿潤養生を終えた直後においても、表面の急激な乾燥を避ける必要がある。このようにコンクリート表面の急激な乾燥を避けることにより、空気中の炭酸ガスがコンクリート内部に浸透し、 内部で不溶性の炭酸塩を形成させることによっても、表面に生ずる白華現象を抑制 することができる。白華現象が冬季は、温度が低く、湿度が低いためコンクリートの凝結が遅くなる傾向があるからである。 欠陥のない緻密な膜を形成させるためにコンクリート表面には材料分離がなく、入念に締固めおよび仕上げを行うなどの施工上の配慮が重要となる。また、コンクリート表面の密度を高くしたり、表面に不透水膜を 形成させる混和材料や塗装材料があるので用いるのがよい。 コンクリート製品などでは、コンクリート成形後にビニルシートやプラスチック フィルムでコンクリートを覆うだけで急激な乾燥が避けられ、白華現象を抑制できる場合もある。
エフロの除去方法について
エフロのうち第一次エフロは可溶成分であるために水で簡単に洗い流すことが出来ますが、第二次エフロは難溶性の炭酸カルシウムが主成分であることから、塩酸などの酸で洗えば簡単に除去することはできます。ただし、酸で洗うことによりコンクリート自体が損傷を受けるので注意が必要である。エフロは2 ~ 3 ヶ月で自然に消えて無くなることもあるが自然に白華が消えるまでの期間は、気象・環境条件 によっては2年以上かかることが多い。可能な限り経過を観察することが望ましいと言えますが、どうしても除去する必要がある場合には塩酸での洗浄が効果的です。
白華は、アルカリ生成物であることより塩酸などで簡単には取れます。塩酸による洗浄には十分な水分を養生し、薄めた(2~3%程度まで薄めます)塩酸をコンクリート表面にかけブラシでゴシゴシこすります(酢などを水に溶かした弱酸性の水溶液を用いてもよい)、 1 5~ 3 0秒待ってから、多量の水で再び洗い 落とす。洗浄は高温の晴天時に行なうのが効果的です。冬季の低温時は洗浄しても表面が乾くまで時間がかかるためエフロを再度発生させる原因となります。白華を酸で洗う場合には事前に水で洗い、コンクリート表面の小穴を水で満たしておくことにより、酸が直接コンクリート中に浸透するのを防ぎ水溶性塩の形で新たに発生する白華を防止するのがよい。第二次白華(エフロ)は、比較的長期の材齢において、雨や結露がコンクリートに浸透して生ずる現象であるため、この白華を防止することは難しいが、基本的には第一次白華の生じにくいコンクリートを用いることにより、ほぼ抑制することができる。 特に、表面に均質で欠陥のない緻密なコンクリートを形成させることが抑制対策 として最有効である。現状のコンクリート技術では、エフロの発生を完全に防止する事は困難なので各種の方法を組合わせてエフロの発生を出来るだけ少なくする様にする事が大切です。