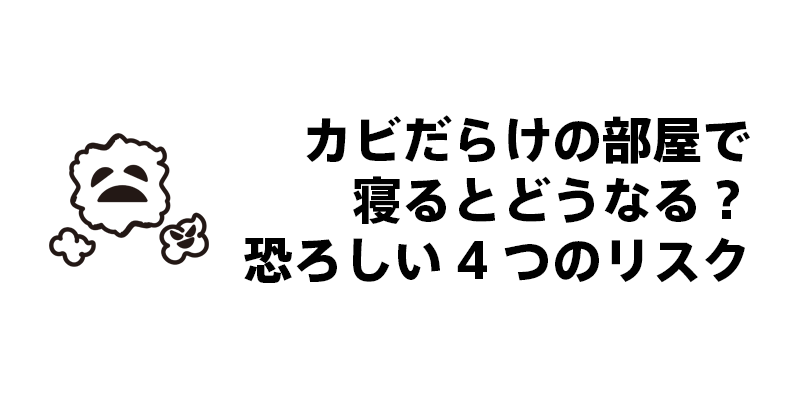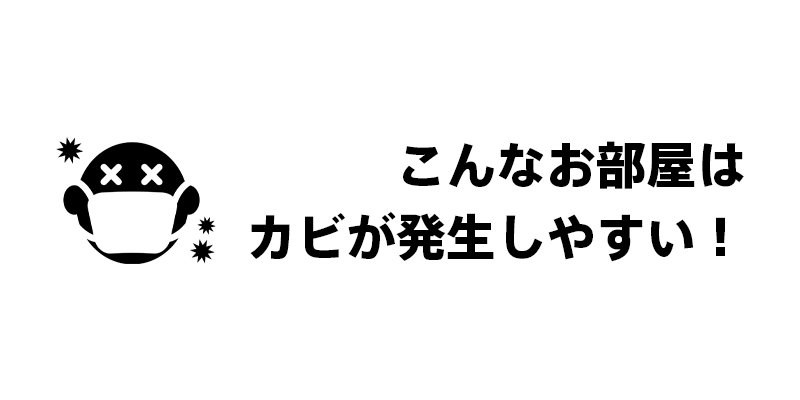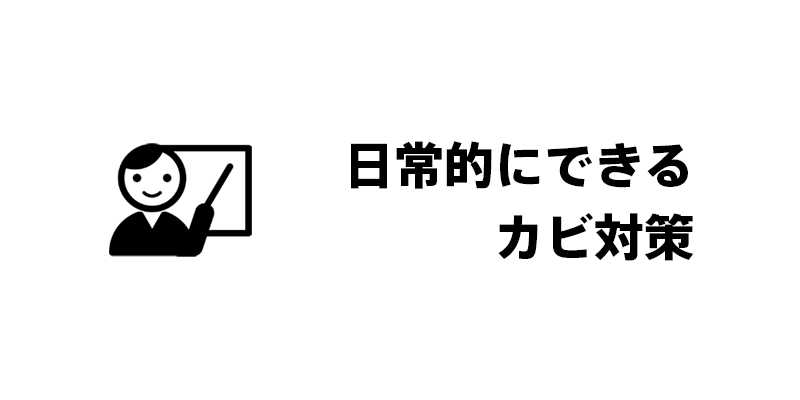カビだらけの部屋で寝るとどうなる?カビのリスクと対策をご紹介!【感染症・睡眠障害etc…】
公開日:2024/02/18
更新日:2026/01/16
カビの正体は、クロカビ(クラドスポリウム属)、コウジカビ(アスペルギルス属)、アオカビ(ペニシリウム属)などのさまざまな菌類です。
カビは、成長すると大きな集合体となり、やがて胞子という細胞を空気中に飛ばし始めます。
このカビの胞子は、さまざまな呼吸器系の病気の原因となる病原体です。
カビをお掃除せず放置していると一体どうなるのでしょうか?
カビだらけの部屋で寝ていると、体にはどんな不調が起こるのでしょうか?
今回の記事では、カビだらけの部屋で寝起きしているとどうなるのかや、カビが発生しやすい環境、カビが生えないようにする対策などについて解説しています。
カビだらけの部屋で寝るとどうなる?恐ろしい4つのリスク
カビは胞子という、目には見えないほど小さな、種のような細胞を空気中に撒き散らしています。
この胞子を人間が吸入すると、体にさまざまな不調が表れることがあります。
この章では、カビだらけの部屋で寝ると、人の体にどのようなリスクがあるのかについて解説していきます。
リスク①アレルギー疾患
カビの胞子は人の喉や鼻、目などの粘膜を介して体の中に侵入してきます。
人の体に備わっている免疫機能は、この胞子を「異物」と判断し、免疫細胞を動員して排除しようとします。
免疫機能が働くと、くしゃみや鼻水、目のかゆみ、肌荒れ、微熱などの免疫反応が体に表れるようになります。
この免疫反応はアレルギーと呼ばれ、悪化すると喘息など、日常生活に支障が出るほどの症状が出るようになることもあります。
カビによる主なアレルギー症状
呼吸器系の症状
- くしゃみ
- 鼻水、鼻づまり(アレルギー性鼻炎)
- 咳、喘鳴(ぜんめい)
- 息苦しさ
- 喘息の悪化
皮膚の症状
- 湿疹、かゆみ
- アトピー性皮膚炎の悪化
目の症状
- 目のかゆみ、充血、涙が出る(アレルギー性結膜炎)
リスク②感染症
カビの胞子が体に侵入すると、通常の体力の人であれば、免疫細胞によって不活化されたり、くしゃみや鼻水などで体の外に排出されます。
ですが、お年寄りや小さなお子様といった体の弱い人の場合は、免疫がカビに負けてしまうことがあります。
免疫に勝利したカビの細胞は、肺や気管支、皮膚などで増殖し、さまざまな感染症を引き起こすことが報告されています。
カビによる感染症の例
肺アスペルギルス症
呼吸器に感染し、咳、血痰、発熱、息切れを引き起こす
ムコール症
副鼻腔、肺、脳、皮膚などに感染し、頭痛、発熱、組織壊死を引き起こす
カンジダ症
口腔内、性器、皮膚、消化管などに感染し、湿疹や排尿痛などを引き起こす
クリプトコッカス症
肺炎、髄膜炎(脳に感染することも)などを引き起こす
白癬(はくせん)、水虫
足、爪、その他の皮膚にかゆみや皮むけ、ただれを引き起こす
リスク③睡眠障害
カビが繁殖した部屋に滞在していると、空気中に放出されたカビの胞子が鼻やのどの粘膜を刺激し、鼻水やくしゃみ、咳などの免疫反応を起こします。
免疫反応は寝ている間にも発生するので、カビが生えた部屋で寝ていると、眠りが浅くなってしまいます。
快適な状態で眠ることができないと、睡眠不足に陥り、日中の集中力が低下したり、居眠りをしてしまうことが増えるほか、免疫が低下するなど生理機能の不調を招くこともあります。
リスク④体臭が臭くなる
カビだらけの部屋で生活をしていると、やがて衣類や寝具などの繊維にもカビが広がっていきます。
特に通気性の悪いマットレスや低反発素材は乾きにくく、内部までカビが侵食すると除去するのが非常に困難になります。
カビが繁殖すると、やがて特有の臭いを発するようになります。
寝具や衣類にカビが発生すると、生乾きのような嫌な臭いが体からするようになってしまいます。
一部の真菌は環境の変化に強く、洗濯や乾燥だけでは死滅させられない場合もあります。
衣類に発生する代表的な真菌であるモラクセラ菌は、乾燥や紫外線に強く、何度洗濯しても時間が経つと復活し、生乾き臭を発生させます。
こんなお部屋はカビが発生しやすい!
カビは、ある一定の条件下で爆発的に繁殖することがわかっています。
お部屋の状態、環境がカビにとって好条件であれば、カビは一気に成長し、あっという間に部屋中のあちこちに広がってしまいます。
この章では、カビが増殖しやすい部屋の特徴について解説していきます。
下記のような環境、状態のお部屋は、カビが爆発的に増えてしまうリスク大!
ご自身のお部屋が条件に当てはまっていないか、ぜひチェックしてみましょう。
カビが好きな部屋①風通しが悪い
部屋に窓が少ない、あるいは開ける習慣がないと、空気がこもり、湿度が下がりにくくなります。
また、換気口や換気扇などが汚れで詰まっていると、空調効率が下がり、空気や湿気がこもりやすくなります。
空気がよどんだ状態は、カビにとって絶好の環境です。
カビが好きな部屋②湿度が高い
加湿器を長時間使っている、洗濯物を室内に干す、といった習慣がある方は要注意。
こうした習慣は、室内の湿度を上昇させ、カビが繁殖しやすい環境を作ってしまいます。
また、冬場であってもカビのリスクはゼロではありません。
冬場に窓ガラスや壁にできる結露で湿度が高くなったり、換気をする回数が減るので空気が篭りやすくなるなど、冬場でも条件が整えばカビが発生することがあります。
カビが好きな部屋③日当たりが悪い
北向きの部屋や、光の差し込みにくい部屋などは、カビの大敵である日光が届きにくく、その分カビのリスクが高まります。
日照時間が短い場所では、壁や床が乾きにくく、常にジメジメとした状態が続き、カビが発生しやすくなります。
カビが好きな部屋④掃除・換気が不十分
床や家具の裏、窓のサッシなどに埃や手垢などの汚れが溜まっていると、それがカビの栄養源になります。
加えて、換気扇を使わなかったり、窓を閉め切ったままの生活を続けると、室内に湿気がこもり、カビが繁殖しやすくなります。
カビが好きな部屋⑤荷物でパンパンの収納スペース
クローゼットや押し入れのような閉ざされた空間もカビが好む場所です。
とくに通気口がなく、ぎゅうぎゅうに物を詰め込んでいると空気が動かず湿気がこもります。
収納内は、荷物を余裕を持って配置する、除湿剤などを設置する、といったカビ対策が欠かせません。
カビが好きな部屋⑥家具や物が多い
物が多すぎる部屋では、空気の流れが遮られ、部屋の隅や家具の裏などに湿気が溜まりがちです。
また、ものが散乱した部屋は掃除が行き届きにくく、埃も溜まりやすいのでカビが繁殖しやすい環境になります。
カビの成長が促進される条件まとめ
| 項目 | 具体的な数値・状態 |
|---|---|
| 温度 | 20~30℃(25℃前後で特に顕著に繁殖) |
| 湿度 | 60%以上(70%以上で特に顕著に繁殖) |
| カビのエサ | 皮脂、汗、埃、石けんカス、木材、紙など |
| 増殖までの時間 | 条件がそろえばすぐに発芽・繁殖数時間〜数日で爆発的に広がる |
| 光 | 暗い場所を好む |
| 通気性 | 空気が動かない、密閉空間を好む |
日常的にできるカビ対策
カビの増殖を防ぐには、カビが増殖しにくくなるような対策を日頃からしておくことが大切です。
この章では、カビの増殖を防ぐ日常的な対策について解説していきます。
カビ対策①換気をしっかりする
換気が不十分な部屋では、湿度がうまく排出されないため、カビが繁殖しやすくなります。
カビの増殖を防ぐには、1日1度、10分程度窓を開けて空気を入れ替えましょう。
換気する際は、リビングの大窓と玄関扉を開けるようにすると、空気が早く入れ替わります。
換気扇を回すのも効果的です。
カビ対策②除湿をする
こまめな換気が難しい場合は、除湿機やエアコンのドライ機能を使ってお部屋を除湿しましょう。
カビは湿度が60%を下回ると活動が鈍くなります。
湿度計を設置し、湿度が60%を超える場合は除湿をするようにしましょう。
カビ対策③こまめに掃除をする
カビを防ぐためには、カビが発生しやすい場所をこまめにお掃除するのが最も効果的です。
カビは、キッチンのシンクやお風呂の排水口、トイレのタンク周辺、洗面所の蛇口まわりなど、水回りに多く発生します。
週に1度はこれらの場所をお掃除し、ゴミを捨て、塩素やエタノールを使って除菌するようにしましょう。
カビの発生源をこまめにお掃除しておくと、その他の場所にカビが拡散するのを防ぐこともできます。
除菌効果のある薬剤
| 薬剤名 | 主成分 | 特徴 | 使用例 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| エタノール(アルコール) | エタノール70〜80%前後 | 即効性があり、広範囲の菌・ウイルスに有効 蒸発が早く、二次汚染を起こしにくい |
ドアノブ、スマホ、台所まわりなどの表面除菌 | 引火性あり ゴムやプラスチックを劣化させる場合がある |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 塩素系漂白剤(例:ハイター) | 強力な殺菌力 菌・ウイルス・カビにも有効 |
浴室、トイレ、排水口などの漂白・除菌 | 金属腐食、衣類の脱色、 塩素臭、塩素ガスに注意 換気必須 |
| 次亜塩素酸水 | 次亜塩素酸(HClO) | 安全性が高く、食品にも使用可能 除菌・消臭両方に有効 |
空間噴霧(推奨されない場合あり) キッチン、冷蔵庫など |
光・熱・時間により効果が失われやすい |
| 塩化ベンザルコニウム(第四級アンモニウム塩) | ベンザルコニウム塩 | 除菌・消臭効果あり 刺激が少なく、手指消毒にも使われることがある |
手すり、机、玩具、洗面台の拭き掃除など | 石鹸との併用に注意(効果減少) 有機物が多い場所では効きにくい |
| 過酸化水素(オキシドール) | H₂O₂(3〜6%) | 殺菌・漂白効果 分解時に有害物質を残さない |
傷の手当て、歯ブラシ・コップの除菌 | 高濃度は取り扱い注意 金属腐食の可能性あり |
| 銀イオン(Ag⁺)系除菌剤 | 銀イオン | 緩やかに長時間除菌が持続 素材を選ばず使用可能 |
スプレー、除菌シートでの拭き掃除 | 即効性はやや低め 濃度により効果が異なる |
カビ対策④1日1回の掃除機がけ
カビがエサにするのは、人の皮脂や髪の毛、食品のカスなどです。
これらのエサが部屋の中に落ちていると、そこからカビが増殖してしまいますので、1日1度は床に掃除機をかけて、カビのエサとなるゴミをしっかり取り除くようにしましょう。
カビ対策まとめ
①換気
窓を開けて10分の換気を1日あたり最低1回以上
②除湿
窓を開けて除湿する。難しい場合はエアコンのドライ機能を使う。
③水回りの掃除
シンク、排水口、トイレタンク周辺、蛇口などの水回りを1日1回程度掃除する。除菌剤を使った殺菌も忘れずに。
④掃除機がけ
1日1回、床に落ちているホコリや食べカスなどを掃除機で吸う。
99%の病原体を殺菌!おそうじ革命のカビ落とし専用洗剤「除菌プロ」
おそうじ革命が水回りのお掃除などに使用している塩素洗剤「除菌プロ」は、現場で培ってきた臨床データを元に、成分を自社で配合したオリジナルの除菌・漂白剤です。
除菌プロは、フィールドテストにおいて、環境中に存在するさまざまな菌・ウイルスを99.9%以上不活化することに成功しています。
また、除菌プロは粘度の高い泡状で散布されるため、市販の塩素洗剤に比べて滞留時間が長く、比較的長時間洗剤をつけおきできるという強みもあります。
そんな除菌プロですが、哺乳瓶の消毒にも使用されている除菌剤をベースに開発されていますので、お子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
おそうじ革命では、高い消毒効果だけど安心安全、そんな除菌プロを活用した水回りクリーニングのほか、お部屋や床、家具などの除菌・消臭サービスもご提供しております。
おそうじ革命のハウスクリーニングサービスを、この機会にぜひご体感ください。