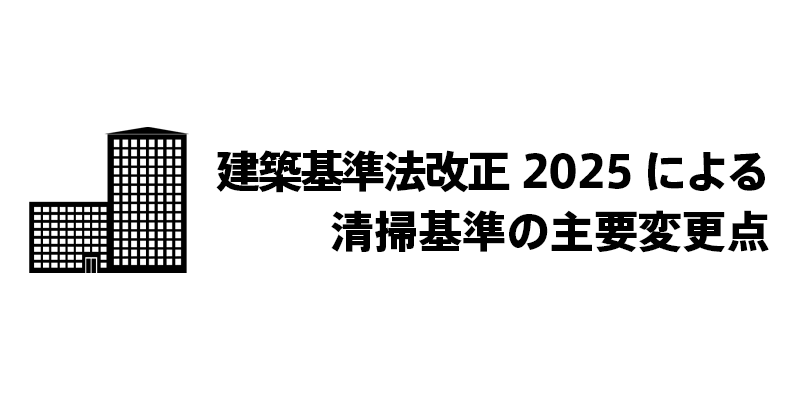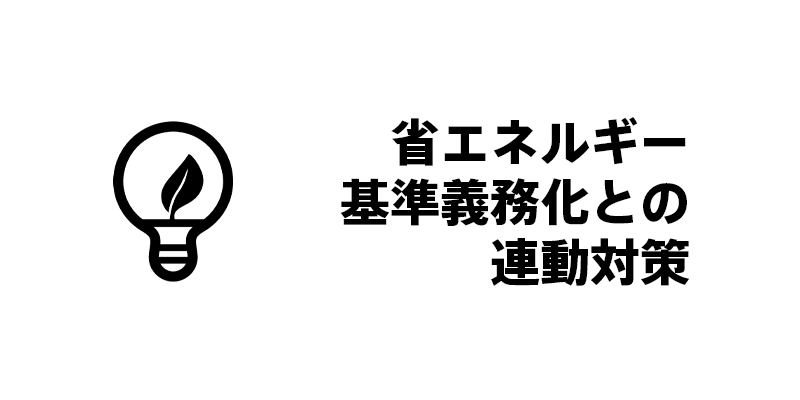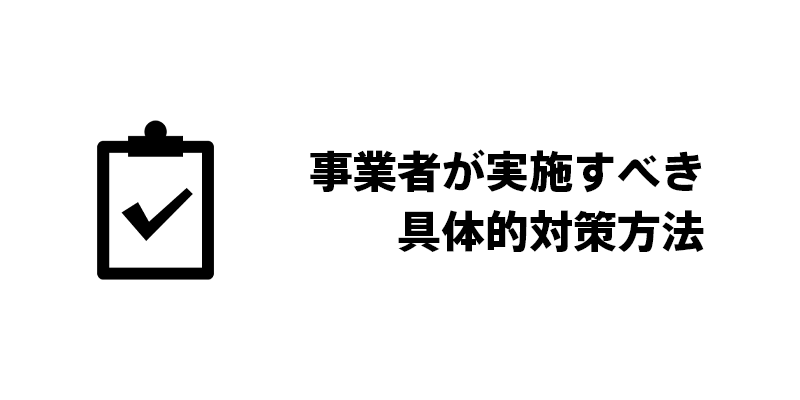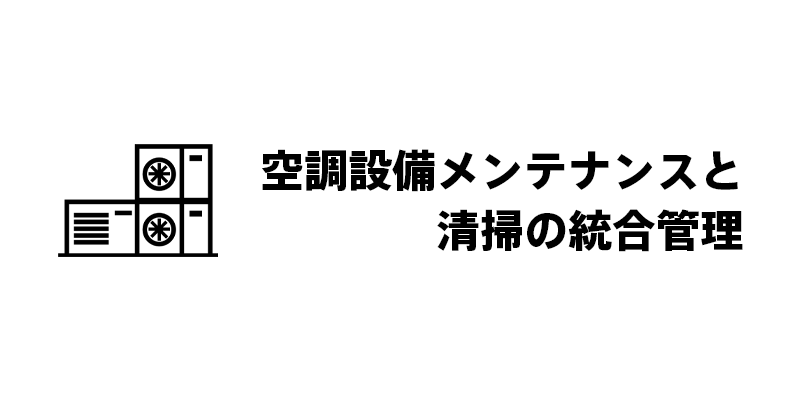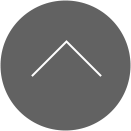建築基準法改正2025で変わる清掃基準とは?事業者が取るべき対策
更新日:2025年09月26日 その他
2025年4月から施行される建築基準法改正により、清掃基準や建物管理に関する規定が大幅に変わります。特に注目すべきは、階数が5以上の場合、特定建築物の対象範囲が延べ面積3,000㎡以上から1,000㎡以上へ拡大されることで、多くの中小規模オフィスや店舗が新たに清掃義務の対象となります。事業者の皆様には、法改正に先立って管理体制の見直しと具体的な対策が求められており、適切な準備を行うことで法令違反のリスクを避けることができます。
記事のポイント- 建築基準法改正2025では特定建築物の対象が1,000㎡以上へ拡大され、中小規模施設も清掃義務対象となる
- 施設種別ごとに床・壁・天井・トイレなどの清掃回数と範囲が詳細に規定される
- 省エネルギー基準義務化と連動した空調設備メンテナンスと清掃記録の徹底管理が必要
- 自社施設の面積確認から清掃計画見直し、従業員教育まで段階的な対策実施が重要
建築基準法改正2025による清掃基準の主要変更点
特定建築物の対象範囲拡大
2025年4月施行の建築基準法改正では、特定建築物の管理義務対象が延べ面積1,000㎡以上の建物まで拡大されます。これまで3,000㎡以上が対象だった規制が、中小規模のオフィスビルや商業施設も法定清掃基準を満たす必要があります。
この変更により、全国で新たに約15,000棟の建物が管理対象に追加される見込みです。小規模な事業所でも、建築物衛生管理基準に基づく定期的な清掃と記録の保管が義務化されます。
対象となる建物用途は、事務所、店舗、学校、興行場、旅館など多岐にわたり、管理権原者は清掃業務の実施責任を負うことになります。賃貸物件の場合、オーナーと管理会社の責任分担も明確化する必要があります。
空気環境測定と清掃の連動強化
2025年の法改正では、空気環境測定と清掃業務の連動性が強化されます。温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度などの測定結果に基づき、清掃頻度や方法の調整が必要となる場合があります。
特に空調設備のメンテナンスにおいて、フィルター交換と清掃の記録管理が重要視されます。省エネルギー基準義務化と合わせて、建物の断熱性能維持のための定期的な清掃作業も規定されています。
貯水槽清掃義務についても見直しが行われ、10㎥以上の受水槽は年1回以上の清掃が義務化されます。清掃後の水質検査結果も保健所への報告対象となり、記録の保管期間も明確化されています。
省エネルギー基準義務化との連動対策
断熱性能向上義務化への対応
建築基準法改正2025では、すべての新築住宅・建築物に省エネルギー基準適合が義務化されます。この変更に伴い、建物の断熱性能を維持するための清掃管理も重要な要素となります。
断熱材周辺の結露対策として、定期的な換気設備の清掃と点検が必要です。特に梅雨時期や冬季には、カビや結露を防ぐための清掃頻度を増加させる必要があります。
外壁や屋根の断熱性能を維持するために、外装材の清掃と点検も管理対象に含まれます。汚れや劣化による断熱性能の低下を防ぐため、年2回以上の外観清掃が推奨されています。
一次エネルギー消費削減対策と清掃業務
省エネルギー基準の義務化により、建物の一次エネルギー消費量削減が必須となります。空調設備の効率維持のため、定期的なフィルター清掃と熱交換器のメンテナンスが重要な役割を果たします。
照明設備についても、LED照明の清拭と照度測定を組み合わせた管理が求められます。汚れによる照明効率の低下を防ぐことで、エネルギー消費量の最適化を図ります。
太陽光発電設備を設置している建物では、パネル表面の清掃が発電効率に直結するため、専門的な清掃技術と安全管理が必要となります。
「おそうじ革命」では、こうした高所作業を含む専門的な清掃サービスを提供しており、省エネルギー基準に対応した建物管理をサポートしています。
事業者が実施すべき具体的対策方法
自社施設の管理対象確認と現状把握
まず最初に行うべきは、管理している建物の延べ面積と用途の正確な把握です。建築確認申請手続き変更点も含めて、各建物が新たに管理対象となるかを確認する必要があります。
建物台帳を整備し、竣工年月日、延べ面積、主要用途、構造種別を一覧化します。リフォームや増築により面積が変更されている場合は、現在の正確な数値を把握することが重要です。
既存の清掃契約についても見直しが必要で、現在の清掃頻度と法定基準との差異を明確化します。不足している清掃項目や頻度については、追加契約や契約変更を検討する必要があります。
清掃計画の見直しとマニュアル整備
法改正に対応するため、施設種別に応じた清掃計画の全面的な見直しが必要です。各エリアの清掃頻度、使用する清掃資材、作業手順を詳細に規定したマニュアルを作成します。
清掃作業の品質を均一化するため、写真付きの作業手順書を整備します。清掃前後の状態を記録できるチェックリストも併せて作成し、作業の完了確認を確実に行える体制を構築します。
自治体条例対応方法についても確認が必要で、国の基準に加えて地域特有の要求事項がある場合は、より厳しい基準に合わせた計画とします。条例の変更情報も定期的にチェックする体制を整えます。
清掃記録の徹底管理システム構築
法令遵守の証拠として、清掃実施記録の完全な管理体制を構築する必要があります。実施日時、清掃箇所、作業内容、担当者名を含む詳細な記録を残します。
デジタル化による記録管理の効率化も検討し、タブレットやスマートフォンを活用した現場記録システムの導入を推奨します。写真付きの報告書を自動生成できるシステムは、記録の信頼性向上にも寄与します。
記録の保管期間についても法定基準に従い、最低3年間の保存を義務化します。定期的な監査や抜き打ち検査に備えて、すぐに提出できる体制を整備しておくことが重要です。
耐火構造要件変更と清掃業務への影響
建築確認申請手続き変更点への対応
2025年の建築基準法改正では、小規模木造建築の「4号特例」が縮小され、これまで審査が省略されていた建物でも建築確認申請が必要となるケースが増加します。この変更は清掃業務にも影響を与えます。
新たに審査対象となる建物では、設計段階から清掃・維持管理を考慮した計画が求められます。清掃しやすい材料選択や設備配置についても、建築確認の際に検討事項として含まれる可能性があります。
既存建物のリフォーム影響点検においても、清掃アクセスルートの確保や安全性が重視されます。高所作業や狭小空間での清掃に必要な設備や手すりの設置も、改修時の検討事項となります。
防火・避難規定強化と清掃安全対策
防火・避難規定の強化に伴い、清掃作業時の安全対策もより厳格な管理が求められます。避難経路の清掃時には、常に代替ルートを確保し、作業時間の短縮を図る必要があります。
防火扉や防煙垂壁周辺の清掃では、設備の動作を阻害しない清掃方法を選択します。清掃用品の保管についても、防火区画を跨がない配置とし、可燃物の管理を徹底します。
スプリンクラーや火災報知設備への清掃時の配慮も重要で、誤作動を防ぐための作業手順を明確化します。清掃後の設備点検も含めた一連の作業フローを確立する必要があります。
自治体条例対応と実務上の注意点
地域別条例の差異と対応策
建築基準法改正2025の国の基準に加えて、各自治体が独自に定める条例への対応も必要です。東京都や大阪市など大都市圏では、国の基準より厳しい清掃頻度や対象範囲を設定している場合があります。
条例の内容は自治体により大きく異なるため、事業所ごとに該当する条例の確認が不可欠です。特に複数の自治体で事業を展開している企業では、地域別の管理基準を整理したマニュアルの作成が効率的です。
条例の改正情報についても定期的にチェックし、年2回以上の法規制確認を実施することを推奨します。自治体のホームページや関連団体からの情報収集体制を整備しておくことが重要です。
共用部清掃頻度の最適化
マンションやオフィスビルの共用部分では、使用頻度に応じた清掃頻度の調整が認められる場合があります。エントランスやエレベーターなど高頻度使用エリアと、機械室や屋上など低頻度エリアで清掃回数を変えることができます。
ただし、最低基準を下回ることはできないため、各エリアの法定最低清掃回数を把握した上で、効率的な清掃計画を立案します。利用者アンケートや苦情履歴も参考にして、実態に即した清掃頻度を設定します。
季節変動への対応も重要で、梅雨時期や花粉シーズンには清掃頻度を増加させる柔軟な管理が求められます。年間を通じた清掃計画を策定し、必要に応じて見直しを行う体制を整備します。
空調設備メンテナンスと清掃の統合管理
フィルター交換と清掃の一体化
空調設備の効率維持と省エネルギー達成のため、フィルター交換と周辺清掃を一体的に実施する管理手法が注目されています。単なるフィルター交換だけでなく、吹出口や吸込口の清掃も含めた包括的なメンテナンスが必要です。
フィルターの交換周期についても見直しが必要で、使用環境に応じて3か月から1年の範囲で設定します。粉じんの多い環境や利用者数の多い建物では、より短い周期での交換が推奨されます。
交換したフィルターの状態記録も重要で、汚れ具合の写真撮影と数値記録により、次回交換時期の予測精度を向上させます。予防保全の観点からも、定期的な状態監視が効果的です。
ダクト清掃と空気品質管理
建築物衛生管理基準の強化により、空調ダクト内部の清掃も重要な管理項目となります。ダクト内に蓄積した汚れは空気品質の悪化と空調効率の低下を招くため、専門的な清掃技術が必要です。
ダクト清掃の実施時期は、空調使用頻度の低い時期を選択し、清掃作業による建物利用への影響を最小限に抑えます。清掃前後の空気品質測定により、清掃効果を数値で確認することも重要です。
清掃作業では飛散防止対策を徹底し、周辺エリアへの汚れの拡散を完全に防ぐ必要があります。作業完了後の清掃確認と記録保管も、法令遵守の観点から欠かせない業務となります。
建築基準法改正2025への総括
まとめ
- 特定建築物の対象が1,000㎡以上に拡大され、中小規模建物も清掃義務対象となる
- 施設種別ごとに床・壁・天井・トイレの清掃頻度と範囲が詳細に規定される
- 清掃記録の徹底管理と3年間の保存が法的義務として強化される
- 自治体条例との整合性確保と地域別対応策の策定が必要となる
- 空調設備のフィルター清掃と空気環境測定の連動管理が求められる
- 防火・避難規定強化に伴う清掃作業時の安全対策が重要視される
- 建築確認申請手続き変更により設計段階からの清掃計画検討が必要
- 共用部清掃頻度の最適化と効率的な清掃計画立案が求められる
- ダクト清掃などの専門的メンテナンスの重要性が増加する
- デジタル化による清掃記録管理の効率化と正確性向上が有効である
- 従業員教育と外部委託業者との連携強化が成功の鍵となる
- 法改正を機会とした建物管理体制全体の見直しと改善が効果的である
総括
建築基準法改正2025は、清掃基準の大幅な変更により事業者に新たな対応を求めています。特定建築物の対象拡大と施設種別清掃回数の詳細規定により、従来よりも厳格な管理が必要となります。省エネルギー基準義務化との連動も含めて、包括的な建物管理体制の構築が成功のカギとなります。
事業者は自社施設の現状把握から始まり、清掃計画の見直し、記録管理体制の整備、従業員教育の強化まで、段階的な対策実施が重要です。自治体条例との整合性確保や専門的な空調設備メンテナンスについても、適切な対応が求められます。
「おそうじ革命」では、建築基準法改正2025にも対応した清掃サービスを提供しており、法定基準を満たす清掃計画の策定から実施まで包括的にサポートいたします。法改正への対応でお困りの事業者様は、ぜひ一度お問い合わせください。