

カビキラー?クエン酸?洗濯機のフチにできる汚れに有効な洗剤とお掃除方法を解説!
公開日:2022/01/28
更新日:2026/01/19
水や洗剤を使用して洗濯物をキレイにする洗濯機には、さまざまな性質の汚れが付着します。
洗濯機のフチにできる汚れには、どのようなものがあるのでしょうか?
また、汚れをキレイにするにはどのようなお掃除をすれば良いのでしょうか?
今回の記事では、洗濯機のフチに発生する汚れについて、以下の見出しで解説しています。
洗濯機のフチにつく汚れの正体は?
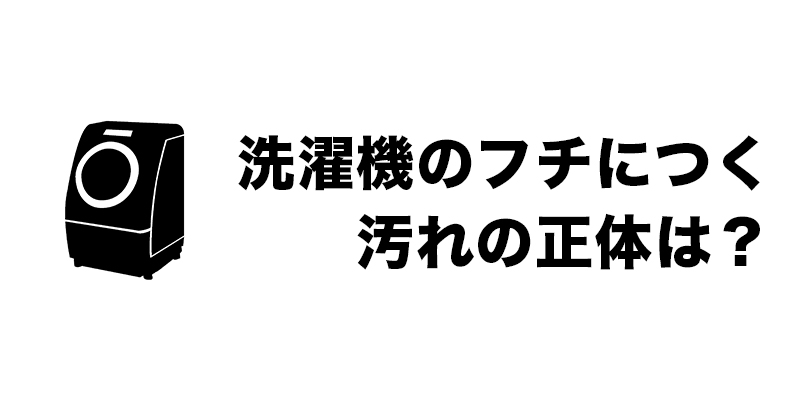
洗濯機の操作パネル周辺や、洗濯槽のフチに発生する汚れには、さまざまな種類のものがあり、汚れの種類によって有効な洗剤が違います。
この章では、洗濯機のフチに発生する汚れの正体と、汚れが発生するメカニズムについて解説します。
洗濯機のフチにできる汚れ①水垢
水道水には、カルシウムなどのミネラルが含まれています。
これらのミネラルは、洗濯機のフチや操作パネルに何かの拍子に水がかかり、それを拭き取らずに放置していると、水分が乾燥した後に下地に残ります。
水垢はアルカリ性の性質を持っているため、油汚れ用のアルカリ洗剤や重曹などには反応しないという特徴があります。
洗濯機のフチにできる汚れ②石鹸カス
石鹸カスは、石鹸や洗濯用洗剤に含まれる脂肪酸などが、水道水と反応したり乾いたりして発生する汚れです。洗濯で使用した洗剤の溶け残りなどが石鹸カスに変化することが多いようです。
石鹸カスは酸性の性質を持っているため、クエン酸や水垢用の酸性洗剤にはあまり反応しません。
洗濯機のフチにできる汚れ③皮脂汚れ
人の指先や汗腺から分泌される皮脂によって、洗濯機のフチが汚れることがあります。
人が触ることの多い操作パネル周辺や、洗濯機の蓋周りなどには、特に皮脂汚れが堆積しやすい傾向にあります。
皮脂汚れは、ゴキブリなどの害虫や、バクテリアなどの有害な微生物のエサとなるため、放置していると不衛生な状態になってしまいます。
皮脂汚れも酸性の性質があるため、クエン酸などの酸性洗剤とはあまり反応しません。
洗濯機のフチにできる汚れ④カビ
カビの正体はカビ菌という菌類で、水分を好み、有機物を食べて成長します。
洗濯後の洗濯機には、湿気が大量に残っており、また、洗濯物から落ちた皮脂や髪の毛などの有機物も豊富にあるため、洗濯機にはカビが発生するリスクが常にあります。
カビ汚れはほっておくとどんどん拡大してしまうため、早い段階でカビの胞子を殺菌し、カビの息の根を止めてしまうことが大切です。
カビの除菌には、カビキラーやハイターなどの塩素洗剤が使われます。
洗濯機のフチについた汚れをキレイにする掃除方法
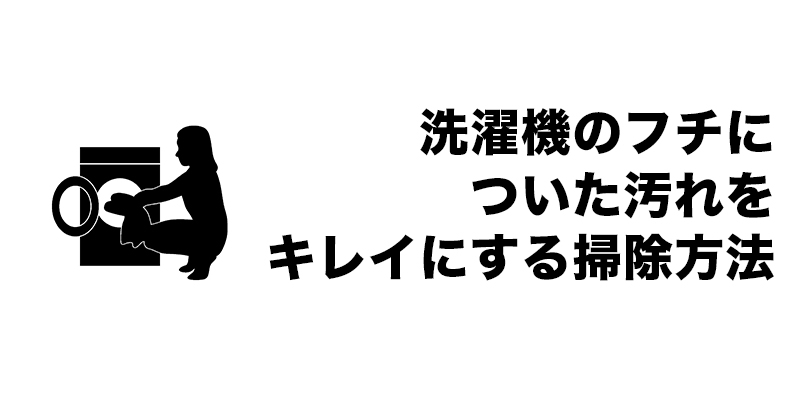
前章で、洗濯機のフチにはさまざまな汚れが付着することがわかりました。
そして、これらの汚れはそれぞれ性質が異なり、有効な洗剤も違います。
この章では、汚れの種類に応じた有効な洗剤と、お掃除の方法について解説します。
①水垢の落とし方
水垢は、水道水に含まれるミネラルが凝固したものです。
水垢はアルカリ性の性質があるため、反対の性質を持つ酸性の洗剤で中和すると、組織が柔らかくなり、落としやすくなります。
家庭用の酸性洗剤は、代表的なものにクエン酸があります。
水垢の落とし方は、まず水垢に洗剤を直接噴射し、ブラシなどで擦って伸ばします。
そのまま10分ほど放置したら、上から激落ちくんなどのメラミンスポンジで擦り、汚れを研磨して落としましょう。
頑固な水垢は、洗剤とスポンジ研磨ではキレイにできない場合があります。その場合は、ヘラなどを使って削り落としましょう。使わなくなったプラスチック製のカードなどを使うのも有効です。
②石鹸カスの落とし方
石鹸カスは水垢と違い、酸性の性質を持っていますので、アルカリ性の洗剤で落とします。
アルカリ性の洗剤は、家庭用のものでは重曹やセスキ炭酸ソーダなどが有名です。
500mlのスプレーボトルに小さじ一杯の重曹orセスキ炭酸ソーダを入れ、残りを水で埋めて希釈したものを用意しましょう。
石鹸カスは構造上、洗剤が浸透しにくいことがあるので、まず最初にヘラなどを使って表面をあらかた削ってから洗剤を塗布すると非常に効果的です。
洗剤の溶け残りなどの石鹸カス汚れを見つけたら、まずは乾燥した状態でヘラやプラカードを使って削り、残った部分に洗剤をかけてスポンジで擦りましょう。
③手垢・皮脂汚れの落とし方
手垢や皮脂汚れは、石鹸カスと同じ酸性の汚れですので、アルカリ性の洗剤が有効です。
ただし、アルカリ洗剤は性質が強いので、心配な方は中性洗剤を使用しましょう。中性洗剤には界面活性剤という成分が含まれており、汚れを対象から剥がし、再度付着するのを防いでくれる効果があります。
中性洗剤は成分が安定しているので、人の肌に触れてもあまり害がないという特徴があります。
フロア用のマジックリンやマイペットなどが家庭用の中性洗剤です。手垢や皮脂汚れを見つけたら、濡らした雑巾に中性洗剤を噴射し、泡と反応させながら拭いていきましょう。
一度で落ち切らない場合は、何度か同じ工程を繰り返しましょう。
④カビの落とし方
カビは生きている汚れです。そのため、キレイにするには洗剤を使ってカビの息の根を止める必要があります。
カビの殺菌によく使われるのは、ハイターなどの塩素洗剤です。
塩素には非常に強い殺菌効果があり、ほとんどのカビに有効です。
ただし、塩素には漂白効果があるため、衣服などに付着すると色落ちすることがあります。
お掃除の際は、洗濯機から洗濯物を取り出した状態で、汚れてもいい服装に着替えて作業しましょう。
また、塩素は吸入し続けると気分が悪くなることがありますので、お掃除は短時間で、かつ十分に換気しながら行ってください。
カビ汚れに洗剤を塗布したら、そのまま5分程度放置してつけおきしましょう。洗剤がカビに浸透し、十分な殺菌効果を得るには、つけおきが欠かせません。
つけおきが終わったら、しっかりと雑巾で拭き取るか、洗濯槽内部など水が流せる部分はしっかり水を流して洗剤を除去しましょう。
洗濯機のフチに汚れが溜まらないようにするには?
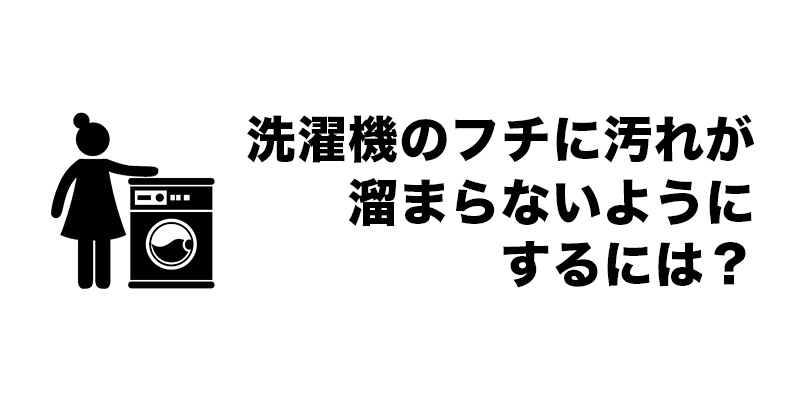
洗濯機のフチに汚れが溜まらないようにするには、日頃からこまめにお手入れをすることが大切です。
この章では、洗濯機のフチに汚れが溜まるのを予防するテクニックについて解説します。
①水分はしっかり取る
水垢を防ぐには、水道水が洗濯機のフチに付着したまま乾燥してしまうのを予防する必要があります。
洗濯が終わったあとは、洗濯機のフチや操作パネルを乾いた布で拭くなどして、水道水が残ったままにならないようにしましょう。
②洗濯機の蓋を開けておく
洗濯機の中に湿気が残っていると、カビなどが発生するリスクが高まります。
洗濯槽の裏側にカビが発生すると、洗濯水にカビやその他の菌類が混じり、それらが洗濯物に付着してニオイの原因になる場合もあります。
洗濯後は洗濯機の蓋を開け、洗濯機の内部にしっかり風が通るようにしておきましょう。
③月に一度は洗濯槽のお掃除を
洗濯槽の裏側は、人の手が届かない部分です。
基本的に直接お掃除ができませんので、汚れやカビが溜まりやすい状態になっています。
月に一度は洗濯槽用洗剤を使用して、槽洗浄モードや洗濯機を空回しして洗濯槽のお掃除をしましょう。
洗濯物の臭いが気になる方は、本格的な洗濯槽のお掃除を定期的に実施しましょう。
洗濯機のフチだけじゃない!パーツを全て分解して手洗いします!おそうじ革命の洗濯機分解クリーニング

おそうじ革命が提供している洗濯機分解クリーニングは、ご家庭の洗濯機を洗濯槽と本体に分解し、それぞれのパーツを一つ一つ丁寧に手洗いでキレイにいたします。
洗濯槽の洗浄に使用する洗剤は、おそうじ革命オリジナル洗剤の「除菌プロ」です。除菌プロは、フィールドテストにおいて、99%の病原菌・微生物の除菌に成功した、殺菌・消毒力に優れた洗剤です。
洗濯機のフチなど、人の手でお掃除するのが難しい場所も、分解してお掃除しますので徹底的にキレイになります!
洗濯物から変な臭いがする、洗濯物にゴミや毛玉が付着する、洗濯機を一度もお掃除したことがない、といったことに心当たりのある方は、是非ともこの機会に洗濯機分解クリーニングをお試しください!





